ˆة“¤ڈہپA“ىژO—¤’¬ژu’أگىکpژ‹ژ@
پ›ژ‹ژ@“ْ’ِپF—كکa‚V”N‚PŒژ25“ْپi“yپjپ`26“ْپi“ْپj
پ›ژ‹ژ@ڈêڈٹپF‹{ڈ錧ŒIŒ´ژsˆة“¤ڈہپE“àڈہپA“ىژO—¤’¬ژu’أگىکpپA‘هچèژs•“ŒIڈہ
پ›ژQ‰ءژزپFژل”ِ—ژ–’·پAàVŒû•›—ژ–’·پAڈ¬—ر(–)•›—ژ–’·پA‰حŒ´کaچDژپپA’†گى—ژ–پAڈ¬—ر(”ژ)—ژ–
‚PپD“ىژO—¤پEٹC‚جƒrƒWƒ^پ[ƒZƒ“ƒ^پ[پiˆؤ“àپE‰ًگàپF•½“cƒZƒ“ƒ^پ[’·پj
ژu’أگىکp‚حپA–¦ٹش‚ج‹——£‚ھ‚Xkm‚ظ‚ا‚ج—¤‘¤‚ةچL‚ھ‚é•آچ½“IٹCˆو‚إپAˆê”شگ[‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚حگ…گ[‚ھ70m‚ة‚ب‚é‚»‚¤‚إ‚·پB‚±‚جڈêڈٹ‚حپAکp‚ة—×گع‚·‚é“ىژO—¤’¬‚جگ…‚ھ—¬‚êچ‚ق•ھگ…—ن‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒIƒIƒqƒVƒNƒC‚âƒ}ƒKƒ“‚ج’‡ٹش‚إ‚ ‚éƒRƒNƒKƒ“‚ھ‚ـ‚ئ‚ـ‚ء‚ؤ”ٍ—ˆ‚·‚éڈêڈٹ‚ئ‚µ‚ؤ—L–¼‚إپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚à•غ‘S‚ھگ}‚ç‚ê‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپA2019”N‚ةƒ‰ƒ€ƒTپ[ƒ‹ڈً–ٌژ¼’n‚ة“oک^‚³‚êپAچ،”N“x‚ح600‰Hˆبڈم‚ج”ٍ—ˆ‚ھٹm”F‚³‚ꂽ‚»‚¤‚إ‚·پB–K‚ꂽژٹْ‚ة‚حپAƒeƒ‰ƒX‚©‚ç200پ`250‰H‚ھٹm”F‚إ‚«‚é‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚½پBƒRƒNƒKƒ“‚حٹC‘”‚ًژهگH‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚ ‚ـ‚èگ[‚‚ـ‚إ‚حگِ‚ê‚ب‚¢‚½‚كپAƒIƒIƒoƒ“‚ھگِ‚ء‚ؤچج‚ء‚½ٹC‘”‚ً’D‚ء‚ؤگH‚ׂؤ‚¢‚邱‚ئ‚à‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پBƒRƒNƒKƒ“‚ئƒIƒIƒoƒ“‚جکJ“‹¤گ¶‚ئ‚ب‚éچs“®‚إ‚·‚ھپA•پ’iگVٹƒ‚إ‚à‰½‹C‚ب‚Œ©‚ؤ‚¢‚éƒIƒIƒoƒ“‚جŒ’‹C‚بˆê–ت‚ًٹ_ٹشŒ©‚ـ‚µ‚½پB

ژu’أگىکp‚حپAژO—¤•œ‹»چ‘—§Œِ‰€“à‚ة‚ ‚èژ©‘RŒِ‰€–@‚ة‚و‚ء‚ؤژç‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“ىژO—¤’¬‚حگl‚ئژ©‘R‚ئ‚ج‹——£ٹ´‚ھ‹ك‚¢‚±‚ئ‚ھ“ء’¥‚¾‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA’g—¬‚âٹ¦—¬‚ھŒً‚ي‚éپAژ©‘Rٹآ‹«‚ج•د‰»‚ھŒƒ‚µ‚¢ڈêڈٹ‚إ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پBکp“à‚إ‚حƒzƒ„پAƒzƒ^ƒeپAƒJƒLپAƒڈƒJƒپپA‹âچّ‚ج—{گB‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA2022”Nپ`2023”N‚ة‚©‚¯‚ؤ•½‹دگ…‰·‚ھ‚Uپژڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پAƒzƒ„‚ح‘S‚ٹl‚ꂸ‚ةپA‹âچّ‚ح–ك‚ç‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚»‚¤‚إ‚·پB
پ@‚ـ‚½پAٹCگ…‰·‚جڈمڈ¸‚ة”؛‚ء‚ؤ“ى•ûŒn‚ج‹›ژي‚ھŒ©‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ـ‚إŒ©‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½“ى•ûŒn‚ج‹›ژي‚إ‚ ‚éƒAƒCƒS‚حپAٹC‘”‚ًگH‚ׂ鋛‚إ‚ ‚邽‚كپAƒEƒj‚ئƒAƒCƒS‚ج‰e‹؟‚إکp“à‚جٹC‘”‚ھŒ¸ڈ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚جژ–‚إ‚·پB‚R‚آ‚جٹC—¬‚ھŒً‚ي‚éژu’أگىکp‚حپA’n‹…‰·’g‰»‚ج‰e‹؟‚ًˆê”شژَ‚¯‚â‚·‚¢ڈêڈٹ‚ب‚ج‚إ‚ح‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ê‚ً“`‚¦‚ؤ‚¢‚‚ج‚ھƒZƒ“ƒ^پ[‚ج–ً–ع‚إ‚ ‚é‚ئ‚¨کb‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
‚QپD•“ŒIڈہپiˆؤ“àپE‰ًگàپF“ˆ“c“NکYژپپj
پ@•“ŒIڈہ‚إ‚حپA–K‚ꂽژٹْ‚ة6–œ‰H‚جƒ}ƒKƒ“‚ھ‰z“~‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إپAŒكŒم‚Sژ”¼چ ‚©‚ç“ْ–v‰ك‚¬‚ـ‚إ‚ث‚®‚ç“ü‚è‚ًٹدژ@‚µ‚ـ‚µ‚½پB

ڈ‰‚ك‚حڈ¬‚³‚بŒQ‚ê‚ھڈ‚µ‚¸‚آڈہ‚ة–ك‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپAŒكŒم‚Tژ‘OŒم‚‚ç‚¢‚©‚ç‚حپA‘ه‚«‚بŒQ‚ê‚ھ‘±پX‚ئڈہ‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚‚و‚¤‚ة‚ب‚èپA‚»‚جژp‚ح‘sٹد‚إ‚µ‚½پB•—‚ح‚ب‚‰ك‚²‚µ‚â‚·‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA“ْ‚ھ‰A‚ء‚ؤ‚©‚ç‚ح’ê—₦‚ھŒƒ‚µ‚پAƒ}ƒKƒ“‚ج‚ث‚®‚ç“ü‚è‚ةگS‚ح‰·‚ـ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‘ج‚ح‚¾‚¢‚ش—₦‚½ٹدژ@‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
‚RپDˆة“¤ڈہپE“àڈہƒTƒ“ƒNƒ`ƒ…ƒAƒٹƒZƒ“ƒ^پ[پiˆؤ“àپE‰ًگàپF“ˆ“c“NکYژپپj
پ@ˆة“¤ڈہ‚حٹC”²‚ھ‚U‚چ‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚½‚ھپAٹC‚ـ‚إ‚ج‹——£‚ھ50km‚à‚ ‚邽‚كپA”rگ…‚ھˆ«‚گ…‚ھ‚½‚ـ‚è‚â‚·‚¢ڈêڈٹ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پBگ…گ[‚حˆê”شگ[‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ1.6m‚ظ‚اپB
پ@ƒ}ƒKƒ“‚ح“c‚ٌ‚ع‚إƒRƒپ‚ًگH‚ׂؤ‚¨‚èپA‰c”_‚ھƒ}ƒKƒ“‚ًژx‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·پB‹{ڈ錧‚إ‚حپAڈہ‚ة‚¢‚é‚ج‚حƒIƒIƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE‚إپAگى‚ة‚¢‚é‚ج‚ھƒRƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE‚¾‚»‚¤‚إ‚·پBƒIƒIƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE‚حپA“ْ’†‚إ‚àˆة“¤ڈہ‚ة‚ئ‚ا‚ـ‚èپAƒŒƒ“ƒRƒ““™‚ًگH‚ׂؤ‚¢‚ـ‚·پBˆة“¤ڈہ‚جƒŒƒ“ƒRƒ“‚ح–kŒہ‚¾‚»‚¤‚إ‚·‚ھپAˆة“¤ڈہ‚ح“€Œ‹‚µ‚ة‚‚¢‚±‚ئ‚ھ–kŒہ‚ج——R‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚µ‚½پB
ˆة“¤ڈہ‚إ‚حژ©‘Rچؤگ¶‚ھگi‚ك‚ç‚êپA1980”N‘م‚جژ©‘Rٹآ‹«‚ً•œŒ³‚·‚邱‚ئ‚ً–ع•W‚ةژ–‹ئ‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBگ…گ¶گA•¨‚حپA–„“yژيژq‚©‚ç20گ”ژي—ق•œŒ³‚µ‚½گ¬‰ت‚ھ‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پBˆة“¤ڈہ‚إ‚حپAˆêژٹْ‚ةƒuƒ‰ƒbƒNƒoƒX‚ھ‘‰ء‚µ‚ؤگ¶‘شŒn‚ھ•د‰»‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پBگHٹQ‚ة‚و‚ء‚ؤڈ¬‚³‚ب‹›—ق‚ھŒ¸ڈ‚µ‚½‚±‚ئ‚إپAƒJƒCƒcƒuƒٹ‚âƒ~ƒRƒAƒCƒT‚ھŒ¸ڈ‚µپA‘ه‚«‚ب‹›‚ًگH‚ׂéƒJƒ“ƒ€ƒٹƒJƒCƒcƒuƒٹ‚ھ‘‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پBŒ»چف‚حپAگlŒûژY—‘ڈ°‚جگف’u‚â“d‹CƒVƒ‡ƒbƒJپ[ƒ{پ[ƒg‚ًٹˆ—p‚µ‚ؤ‚©‚ب‚è‚جگ”‚ًŒ¸‚ç‚·‚±‚ئ‚ةگ¬Œ÷‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB2009”Nˆبچ~‚حپA‹›—ق‚جŒآ‘جگ”‚ح•œٹˆ‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚©‚آ‚ؤ‚¢‚½ƒ^ƒiƒS‚ھƒ‚ƒcƒS‚âƒ^ƒ‚ƒچƒR‚ة•د‰»‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA2021”N‚ة‚حƒ[ƒjƒ^ƒiƒS‚ھ•œٹˆ‚µ‚½ٹً‚µ‚¢ƒjƒ…پ[ƒX‚ھ‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إپA‰حگى‚ج—¬ˆو‚إ‚ج‚آ‚ب‚ھ‚è‚ھپAژ©‘Rچؤگ¶‚ة‚à‘ه‚«‚ٹضŒW‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‹»–،گ[‚©‚ء‚½‚إ‚·پB

پ@ƒXƒڈƒ“ƒvƒچƒWƒFƒNƒg‚حپAƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE‚جˆت’u‚ھƒٹƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ€‚إٹm”F‚إ‚«‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAڈî•ٌ‚ھŒِٹJ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邽‚ك‚ة’N‚إ‚àŒ©‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«پA‚ـ‚½پAٹeŒآ‘ج‚ةˆ¤ڈج‚ً•t‚¯‚½‚±‚ئ‚ھ‰وٹْ“I‚بژو‘g‚ف‚إ‚ ‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚µ‚½پBژ–‹ئ‚ً’ت‚µ‚ؤپAژs–¯‚ئˆêڈڈ‚ةƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE‚ًŒ©ژç‚éپuژs–¯‰بٹwپv‚ئ‚µ‚ؤپA‘½‚‚جگl‚ةٹضگS‚ًژ‚ء‚ؤ‚à‚ç‚¢‚½‚¢‚ئٹ´‚¶‚ـ‚µ‚½پB
پ@ژ–‹ئ“™‚ًگà–¾‚¢‚½‚¾‚¢‚½Œم‚ة‚حپAٹظ“à‚àˆؤ“à‚¢‚½‚¾‚«پA‚»‚جŒم‚حƒGƒRƒgپ[ƒ“‚جچؤگ¶‚ج—lژq‚â“o•ؤژs‚ج’Wگ…‹›ٹظ‚ب‚ا‚ًŒ©ٹw‚µ‚ـ‚µ‚½پB
‚SپD’·ڈہچ»Œ´گ…–ه‹y‚ر‰z—¬’ٌپi‰ًگàپFڈ¬—ر–’j•›—ژ–’·پj
پ@’·ڈہ‚حپAˆة“¤ڈہ‚ج“ى“Œ•”‚ةˆت’u‚·‚é‹{ڈ錧“àچإ‘ه‹‰‚جŒخڈہ‚إ‚·پB•½گ¬26”N‚ة’·ڈہƒ_ƒ€‚ھٹ®گ¬‚µپAچ^گ…‘خچô‚ئ‚µ‚ؤپA”—گى‚©‚ç‰z—¬’ٌ‚ً’ت‚µ‚ؤ’·ڈہ‚ً—Vگ…’n‚ئ‚µ‚ؤ’™گ…‚·‚é‹@”\‚ًژ‚½‚¹‚ـ‚µ‚½پB”—گى‰ˆ‚¢‚ة‚ح1km‚ة‹y‚ش‰z—¬’ٌ‚ھ‘¢‚ç‚êپA‚»‚±‚©‚ç’·ڈہ‚ـ‚إ‘S’·2.7km‚ة‹y‚ش“±گ…کH‚ھگ®”ُ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

“ˆ“c“NکY‚³‚ٌ‚ج‚¨کb‚ة‚و‚é‚ئپAگ®”ُŒم‚ة‚Q‰ٌ‚ظ‚ا‘ه‰J‚ج‚½‚ك‚ة’تگ…‚µ‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚é‚»‚¤‚إ‚·پB“±گ…کH“üŒû•t‹ك‚إ‚حپAƒTƒM—ق‚جŒQ‚ê‚ھ‹x‘§‚·‚é—lژq‚ب‚ا‚àٹدژ@‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB
‚TپDژ‹ژ@‚ج—lژq

“ىژO—¤پEٹC‚جƒrƒWƒ^پ[ƒZƒ“ƒ^پ[ٹظ“à‚ج—lژq‡@

“ىژO—¤پEٹC‚جƒrƒWƒ^پ[ƒZƒ“ƒ^پ[ٹظ“à‚ج—lژq‡A
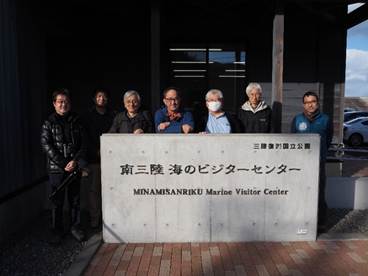
“ىژO—¤پEٹC‚جƒrƒWƒ^پ[ƒZƒ“ƒ^پ[•½ˆنƒZƒ“ƒ^پ[’·‚ئˆêڈڈ‚ة

“r’†—§‚؟ٹٌ‚ء‚½‹Œ“ىژO—¤’،ژة‚ج—lژq

•“ŒIڈہ‚ث‚®‚ç“ü‚èٹدژ@‚ج—lژq‡@

•“ŒIڈہ‚ث‚®‚ç“ü‚èٹدژ@‚ج—lژq‡A

ˆة“¤ڈہپE“àڈہƒTƒ“ƒNƒ`ƒ…ƒAƒٹƒZƒ“ƒ^پ[“à•”‚ج—lژq‡@

ˆة“¤ڈہپE“àڈہƒTƒ“ƒNƒ`ƒ…ƒAƒٹƒZƒ“ƒ^پ[“à•”‚ج—lژq‡A

ˆة“¤ڈہپE“àڈہƒTƒ“ƒNƒ`ƒ…ƒAƒٹƒZƒ“ƒ^پ[“à•”‚ج—lژq‡B